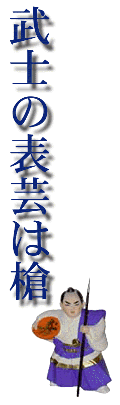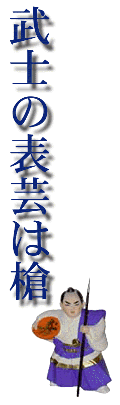|
武士の表芸は槍です。
スポーツ・チャンバラで得物を自由にすると誰もが薙刀を取ります。足を薙ぎることは強いです。女子が薙刀を持つのがうなずけます。
弁慶も、やはり薙刀でした。
小太刀と短刀の試合をすると、意外に短刀が勝ちます。振りかぶる間に、まっすぐに手を下から振り子のように刺し入ります。小太刀と長刀では、やはり長刀が強いです。
長刀と槍では、圧倒的に槍が強いです。しかし、二刀を持つと槍に肉薄します。
長槍と短槍では短槍の方が強いです。
赤穂浪士の討ち入りで「得物はかってたるべし」と大石が連絡すると、ほとんどが槍を持って参上したようです。
実際に小太刀で女子と練習をするときはかなり余裕でやっていますが、同じ女子が槍を取ると私の身体中が臨戦態勢に入り、毛が逆立ちます。槍との対戦にはそれほどハンディがあるということです。
馬の上で使った太刀は、長くそっていて振り回して使いました。刀は昔の鎧には刃が立たなかったようです。
刀の歴史をみると世の中が騒乱状態では慶長新刀のように実践的な肉厚大振な刀が流行り、振りやすい鉄の棒的になります。太平の世では腰に軽く負担が少なく振り回しやすい、軽く短い物が好まれています。
斬るより刺したほうが効率がよいことがわかってくると、ソリの少ない直刀の体裁になってきます。特に居合的要素が強い時代になると、より一層ソリは緩くなります。刀は実用刀と儀仗用に別れ、実践の闘いでは実用刀を数本持ち歩いたようです。
私は10本ほど大小刀を持っていますが、ワラを斬る刀、竹を切る刀、釘でも斬ってみる気の刀、据え物斬り用で青竜刀と争うぐらいの刀、片手で使う小太刀、その他観賞用の刀です。観賞用や居合用ではもったいなくて物は斬れません。
本当の闘いでは、片手に楯を持ち片手に刀を持つのが自然です。フェンシングにしても楯を持って闘った方が強いと思います。
かのローマ軍も腰に刀、左手に楯、右手に槍の出で立ちです。これが命をかけた闘いの出で立ちです。
刀がシンボル的な存在になったとき、本来の武器から違う意味を持ってきました。それでも剣術として残り
|